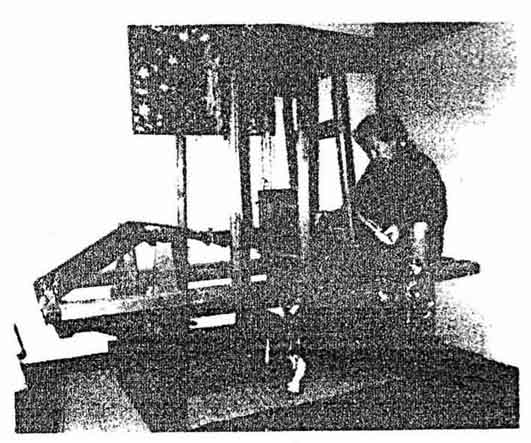田舎では、どこの家でも蚕を飼っていた。掃立てから繭になるまでの作業は、苦労も多く多忙であったが、楽しみなことでもあった。取れた繭は、その殆んどを町の製糸工場に売り、僅かに残ったくず繭を、母は大きな鍋で煮て、うつぎの葉で糸口を引き出し、数本ずつを一緒に取リ出し、1本の糸にして、「プィーン、プィーン」と鈍い音をたて、糸車を廻して紡いだ。
その糸ではたおりを教えてくれた。「わく」に巻き、かせくりにかけ、管に巻き、「はたご」にかけるまでには、数段階の作業をへてやっと機織りが始まり、1反織るに幾日もかけて、丹念に織り続けた。そうして織り上げた白生地は、着物に羽織にと、好みの柄に染めて、みんな私の嫁入支度となった。
嫁いでからは、はたおることもないまま、忘れかけた頃、食料も衣料も統制になり、衣料は切符制になった。育ち盛りの子には着せねばならず、思いついたのが、昔取った杵づかとばかり、はたを織ろうと、名古屋の「やみ市」でわけの分らぬ糸を買ってきて、娘時代の、おぼろげな記憶をたよりに、はたを織った。それは、布とは名ばかりのガサガサの織物だったが、着物に洋服にと仕立てて着せ、苦しい時代をのりこえた。
今でも、效範町の武藤くわさん{明治36年(1903)生}が、趣味としてウールの糸で、時折、織っておられるようです。
平町の横山志ようさん{明治29年(1896)生}は、「古いことで大方忘れてしまったが、昔は、畑で綿を作り、それを紡いで織り上げるまで、全部家でしたもんじゃ。木綿を紡ぐことは難しいので、上手な人でなきゃやれなんだが、織ることは誰でも織ったもんじゃ、布団も、着物も、仕事着も、みんな木綿の、うち織じゃった。表も裏も、うち織で丈夫なこたぁ丈夫じゃったが、重い布団や着物じゃった。今は、エエもんが出来てエエ世の中じゃ、布団も軽うて、ぬくとうて、長生きはするもんじゃ」と、とつとつと話してくださった。